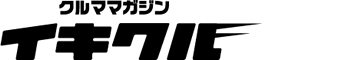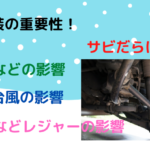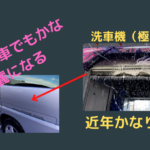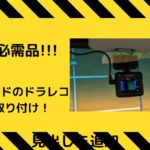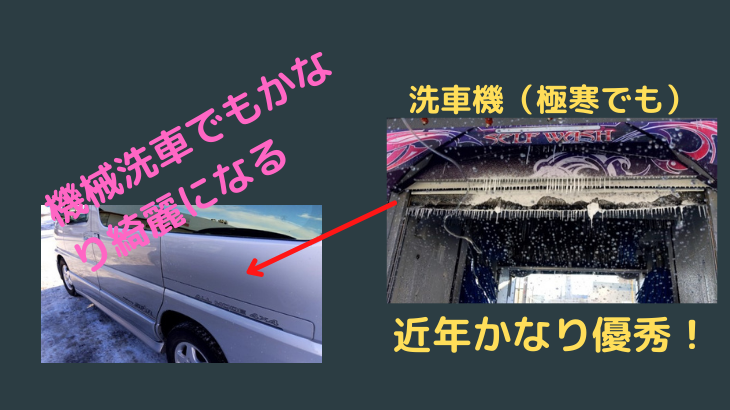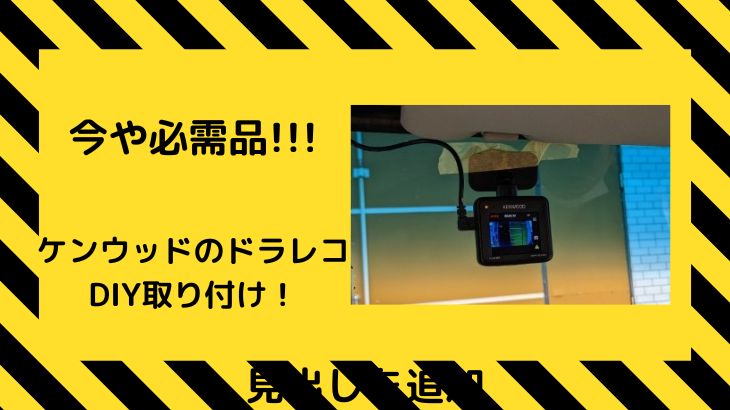トヨタやホンダ、日産といった自動車メーカーを中心とした11社が、平成29年12月12日、FCVの普及を目指す新会社を平成30年春に設立すると発表しました。読者の中には「FCVって何?」と思われた方もいらっしゃるでしょう。確かにEV(電気自動車)と比べて聞きなれない単語ですが、FCVとは燃料電池自動車のことを指します。
世界的にEVの普及が進む中、なぜ今FCVなのでしょうか? 今回はFCVについてはもちろん、代表車種やメーカーの狙いも交えてお伝えします。
FCVは水素で発電する電気自動車

冒頭でも述べた通り、FCVとはFuel Cell Vehicleの略で、直訳すると燃料電池自動車となります。燃料は水素で、水素と酸素を化学反応させることで電気を発生させ、そのエネルギーでモーターを回転させて動力を得る、つまりは電気自動車の一種です。
現在主流となっているEV(電気自動車)には、リチウムイオンバッテリーの容量が少なく従来の自動車に比べて航続距離が少ない、急速充電であっても30分近く充電に時間が掛かってしまうという欠点を抱えています。こうしたEVの欠点に対して、FCVなら燃料である水素の補充には数分程度しか掛かりません。それでいて700km以上というEVはもちろん、従来の自動車をもしのぐ航続距離を確保できてしまいます。水素を燃料とするため排出ガスは発生せず、ガソリンエンジンを搭載するトヨタ・プリウスなどのHV(ハイブリッド車)よりもクリーンだというのもポイントです。

イキクル3周年記念特別企画!現金30,000円プレゼントキャンペーン実施中